撮る,見る,聞く。カメラは感性を表す道具(株)ニコン ニコンフェロー 映像カンパニー 後藤研究室長 後藤 哲朗
写真忘るべからずニコンの機材ありき
聞き手:そうなると,カメラだけではなく,テレビやプロジェクター,プリンターなどをワンセットでそろえている電機メーカーが強いですよね。ニコンが負けないためには?後藤:第37回(2011年度)の木村伊兵衛写真賞を受賞された田附勝さんが,受賞式で面白いことを言われました。「初心忘るべからず,そして写真忘るべからず」と。もう大笑い。田附さんに「それ,もらっていいですか」と許しを得ましたので,社員教育の中でも使っています。ニコンの社員ですから「写真を撮らなきゃ話にならないでしょう!」と。写真を撮って楽しむ人,写真を見て喜ぶ人,そういう人たちのために,「ニコンの機材ありき!」ということを発信し続ける,そういう意味で初心(写真)を忘れてはいけないと言っています。
 1948年にニコンが初めて「I型」という小型カメラを出してから64年になりますが,ニコンは実は新参者なのです。戦前からカメラを生産しているキヤノンやミノルタ(現ソニー)など他のメーカーのほうがずっと歴史があります。確か戦後カメラを始めたのはペンタックスとニコンぐらいではないでしょうか。それから考えますと,そんなにカメラ作りの歴史があるわけではなく,戦前・戦中に光学兵器を製造していた時に培った「丈夫さと信頼性」一点張り,ニコンのものづくりはここに尽きると思います。そういう命の掛かった特殊な機材を世に出していたエンジニア達が,戦後,ビジネス転換を迫られて「カメラでも作ってやろう」となればそれは丈夫なものができるわけですよ。多少武骨で使いにくく,重くて高いかもしれませんが,それが本来のニコンのDNAではないかと思っています。もちろんスタートが光学会社ですので光学(Optics)はそれよりも重要なDNAですけどね。
1948年にニコンが初めて「I型」という小型カメラを出してから64年になりますが,ニコンは実は新参者なのです。戦前からカメラを生産しているキヤノンやミノルタ(現ソニー)など他のメーカーのほうがずっと歴史があります。確か戦後カメラを始めたのはペンタックスとニコンぐらいではないでしょうか。それから考えますと,そんなにカメラ作りの歴史があるわけではなく,戦前・戦中に光学兵器を製造していた時に培った「丈夫さと信頼性」一点張り,ニコンのものづくりはここに尽きると思います。そういう命の掛かった特殊な機材を世に出していたエンジニア達が,戦後,ビジネス転換を迫られて「カメラでも作ってやろう」となればそれは丈夫なものができるわけですよ。多少武骨で使いにくく,重くて高いかもしれませんが,それが本来のニコンのDNAではないかと思っています。もちろんスタートが光学会社ですので光学(Optics)はそれよりも重要なDNAですけどね。聞き手:報道分野でもずっとニコン党の方がいますが,丈夫で信頼性,そして作品のできに対してのプラスアルファがないと,そういった玄人好みは現れないのでは?
後藤:とにかく丈夫で壊れない,という神話がまずできたのが良かったのでしょうね。極寒の戦場など過酷な環境で他の機材がバタバタと壊れたり動かなくなっている中でニコンだけが使え,その結果として現在でも世に残るような作品が撮れたと。中には動かなくなったニコンもあったかも知れませんけれど。さらに一眼レフで言えば,古いカメラでも新しいレンズとの互換性,その逆の互換性もいまだにかなり保っているのも魅力と信頼の1つだと思います。
聞き手:以前,後藤さんがある講演で「今までニコンは技術的な開発は成して来ているが,今後は写真文化そのものの開拓が課題だ」とおっしゃっていますが。
後藤:大きな課題ですね。会社の規模とビジネス規模が大きくなりますと,そうカメラが好きなわけでもないという社員が確実に増えて来ています。ニコンだからまだマシな方だよ,と仰る方もおられますが。また学生さんの気質なのか教育の偏りなのか,アナログ屋がいなくなっているというのはどのメーカーも同じ悩みのようです。その最たるものが,レンズであったり,カメラのたたずまい,音や操作感への関心であったりするのではないかと思いますので,改めて「カメラとは,写真とは何か」に向き合う必要がありますね。
また写真というのは使う人,見る人ありきですから,お客さまが何を期待しているのか,ということを間違いなく理解しなければいけません。そのためには写真や撮影現場を直に見なければ話になりません。クレームや面と向かってお叱りをいただくことが良い薬になりますし,たまには褒められることが自信にもつながります。社内では「会社の外に出て,作品を見て,作家やアマチュアの方たちと話をしてこないと駄目だぞ」と言っています。そして自分で写真を撮って来いと。自分たちでマーケティングしたもの,設計したもの,生産したものが,どれだけ良いものか,あるいは悪いものか,人の意見を聴くだけでなく自分で実感しなければ人に伝えることができないわけです。優秀なカメラ機材を作っていますといいながら,その実カメラの操作ができなかったり,撮ってくる写真がお粗末では説得力がなく駄目なわけです。人のことは言えませんが(笑)。
聞き手:お客さまが求める画像,撮りたいシーンなどそういったものの中から新しい写真の撮り方や文化が生まれてくるのでしょうか。
後藤:生まれてくるし,実際に変わってきますよ。そもそもカメラの小型化などで写真文化が変わった実例はいくつもあります。またカメラ開発の歴史として,お客さまの要求を察知してそれを次の機種に反映し,その様子を見てさらに次に反映,ということを繰り返しています。例えばストロボ,いまや手動で調整するなど考えられないほど自動化を進めました。さらにフィルム巻き上げのモータードライブ,露出,ぶれ防止などの自動化などもあります。「おれたちはプロだから,そんなものいらないよ」と何度言われたことでしょう。最たるものがオートフォーカスです。初期には大きなクレームをいただきましたが,実用になってくると,オートフォーカスができたおかげで「写真生活の寿命が延びた」,「カメラマンとしての命が延びた」と印象が変わってきています。まだまだこのような機能や性能アップは出てくると思います。それを察知するためには,お客さまと話をして,あるいは自分で撮って見て,身に染みさせないと駄目なわけです。私は今でも時折富士スピードウェイなどに実写に行きます。かつては,重いながらもライバルメーカーの機材も持参して,比較実写をしました。最近は疲れ気味ですので重労働は若いメンバーに任せ,ひたすらお話し役をメインとしていますが,実写する傍ら現場におられる大勢のカメラマンの意見を聞いたり,ライバルメーカーの方に「すみません,ニコンですけどどうですか?」などと情報を集めながら,いろいろなフィードバックをしてきました。
聞き手:5月に,デジタル一眼レフカメラ「D800」が「カメラグランプリ2012大賞」「あなたが選ぶベストカメラ賞」をダブル受賞されましたね。
 後藤:ありがとうございます,ダブル受賞は実に珍しい快挙だと思います。D800・D800Eには画素数36メガというすごい飛び道具が入っています。階調性は別として解像度だけで言えば400万円もする中版カメラなどに匹敵する画像センサーが入っていて,連続撮影が利き,しかも35万円程という破格な機材です。
後藤:ありがとうございます,ダブル受賞は実に珍しい快挙だと思います。D800・D800Eには画素数36メガというすごい飛び道具が入っています。階調性は別として解像度だけで言えば400万円もする中版カメラなどに匹敵する画像センサーが入っていて,連続撮影が利き,しかも35万円程という破格な機材です。その他,極限の用途として「ナノクリスタルコート」を施した交換レンズが非常に受け入れられています。これはステッパーで開発した技術を民生品に応用したもので,レンズ中の内面反射を低減させてフレアなど余分なものを最小限にした結果,画像のキレや抜けが抜群にいい。レンズを太陽の方向に向けると,直接はいけませんが,中に綺麗な反射が見えますよね,あれが相当消えますので効能が比較しやすいと思います。そのような威力のあるコーティングがされていますので,アナログの究極であるレンズがあってこその,D800・D800Eであり,久々のヒット作だと思いますね。 <次ページへ続く>

後藤 哲朗(ごとう・てつろう)
1973年,千葉大学工学部電気工学科卒業。同年,日本光学工業株式会社(現?ニコン)入社,機器事業部(現インストルメンツカンパニー)でサーマルカメラ(赤外線カメラ)の開発に従事。1975年,カメラ設計部に異動,フィルム一眼レフカメラ「F3」で電気回路設計,「F4」では電気系リーダー,「F5」ではプロダクトリーダーを勤める。1997年,カメラ設計部ゼネラルマネージャーとして,フィルムカメラシステム全般を指揮。2004年,映像カンパニー開発本部長・執行役員に就任。「D3」などのデジタル一眼レフカメラ,交換レンズ群,コンパクトデジタルカメラ,アプリケーションソフトなど映像製品全般の開発を指揮。2007年,映像カンパニー副プレジデント就任。2009年より現職。








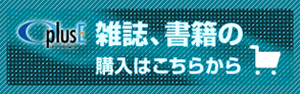
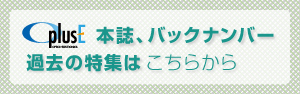

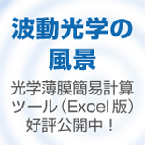







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)