第22回 国際ディスプレイホログラフィーシンポジウム・ISDH ― 始まり・レイクフォーレストカレッジ ―
トリエンナーレ,出会い
TJの夏のホログラフィーワークショップは毎年続けられ,国際シンポジウムはその後,3年に一度のペースで開催されることになる。毎回いろいろな国からの参加者があり,多くの興味深い出会いを経験した。
ある時(2回目のころか?),参加者全員が,夕方から始まるクラシックの野外コンサートに招待された。夏の夜の野外コンサートといえば,NY在住の友人に連れられて,ニューヨークフィルハーモニックのサマーコンサートに行ったことがある。野外ステージが広い公園の中に設えられ,誰でも参加できる無料コンサートに,人々は家族づれでお弁当や飲み物を持ち,ピクニック気分で芝生に寝そべったりしながら贅沢な時間を楽しんでいた。アメリカでは夏のシーズンに,いろいろなところで,このようなイベントが開かれるようだ。レイクフォーレストでは芝生ではなく,スタジアム風の野外コンサート会場であった。緯度が比較的高く(シカゴは函館と同緯度),サマータイムがとられているので,屋外は夜遅くまで薄明るい。涼しい風に吹かれながらのクラシック生演奏はなかなかの体験であった。偶然隣りの席に中国からの招待講演者である北京郵電大学(Bejing University of Posts & Telecommunications)の除大勇(Hsu Dahsung)教授が座っていた。背が高く痩身で物静かな学者という風情のその人は,高齢の印象を受けた。それまで中国との交流にはまったく縁がなく,中国といえば,その7~8年前まで紅衛兵と文化大革命の嵐一色のニュースの印象しかなかった。そのため,本当の中国国内事情に,私は実は興味津々であった。特に,知識階級の人たちにとっては大氷河期時代であったに違いない。英語を自由に話し,クラシック音楽を楽しめる人は,いったい文革時代をどのように過ごしていたのか。興味本位で,実に失礼な質問を,私は彼に単刀直入にぶつけてみた。「クラシック音楽を聴く機会はあるのか?」「文化大革命についてどう考えているか」など,きわどい質問をした。返ってきた答えは「クラシック音楽は好きでよく聞いている」,「文革時代はたいへん苦労の多い時代だった。肉体労働で無理がたたって体を壊し,それでこんなに年を取ってしまった」というような話をしていた。彼の実年齢は風貌よりずっと若いかもしれないと知った。教授とはその後,何度もこのシンポジウムで会うのだが,いつであったか中国の教え子たち数人を連れて参加していた時があった。彼らはまだあまりアメリカ文化には不慣れな様子だった。特に,その中の1人で,英語をほとんど話さない女性は,東洋人のアーティストである私に興味と親しみを覚えたらしくあまりほかの参加者たちの輪には入らず,気づくとよく隣りにいたことを覚えている。
ひろがり
Hsu Dahsung教授とはずっと後,キルギスでの光学シンポジウムでも一緒になったことがあり,とても長い付き合いとなった。彼の教え子たちとも,実は後に不思議な縁が繋がっていた。この,中国からの女性Mrs. Leeは,われわれがアメリカで会った時,すでにエンボスホログラムのセキュリティ関係の会社を立ち上げてその代表だった(Hsu教授は技術的な後援者だったようだ)が,その後会社を大きく成功させ,日本にもビジネスでよく往来していたようだ。ある時彼女から連絡があり東京で旧交を温めたことがあったが,バリバリのキャリアウーマンという感じで,アメリカで初めて会った時の印象とだいぶん違っていたのには面食らった。その時は日本語を話す秘書を連れていた。エネルギーに満ち溢れた上り坂の中国の国情を体現しているような人だった。ちょうどそのころ土肥寿秀氏(元コニカミノルタ㈱,OptiWorks ㈱主宰)は,Mrs. Leeに出会って筆者のことを知ったらしい。土肥氏は彼女から「日本のホログラフィーアーティストにはSetsukoがいるではないか」と言われて初めて筆者のことを知り,ちょうど神田の画廊で個展を開催していた時,突然画廊に見えた。大阪から来られたとのことであったが,開口一番「どうやって食べているの?」という質問には,かなりのインパクトがあった。「なんと失・・・!」のどまで出かかった言葉をぐっと飲み込み,それまで何度も似たような質問を浴びせられて答え方にも知恵がついてきた私は,にっこり笑って「霞を食べて生きています」と答えた。土肥氏は光学の専門家で,ホログラフィーには黎明期から関心を抱いていた分野だったそうだが,その後は特にホログラフィーアートにはまったく接点がなかったようで,中国のMrs. Leeから私の情報を知り,「霞を食べて生きています」の返事も気に入られたようで,ホログラフィーアートへの応用にもたいへん興味をもたれたようだった。この時の土肥氏との出会いが,後のキルギスの訪問につながるのである。キルギスにホログラフィーアートをぜひ紹介しようという提案に,私も賛同した次第である(キルギスのことは第11回本誌OplusE Vol.41, No.5, 2019掲載)。
広がりの話はこれで終わらない。一昨年(2019年),中国の南京を訪問する機会があった。ホロ関連のプロジェクトに招待されたのだが,そのきっかけは,実はレイクフォーレストのシンポジウムにHsu教授に連れられて参加していた,別の教え子によるものであった。四半世紀ぶりの中国からのコンタクトにびっくりしたが,先方はHsu教授からアップデートして私の情報を知っていたようであった。ホログラフィーアートが彼らにどのように受け止められていたかはまったく不明であるが,後にこのような縁に発展していったということは,筆者の仕事(アート)がそれなりに彼らに強い印象を残していた結果であろうか。ともあれ,南京のプロジェクトはこのパンデミックで,結局すべて凍結状態のままである。この先どのようになるかまったく不明だ。
(次回に続く)









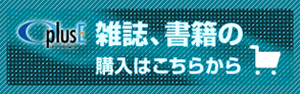
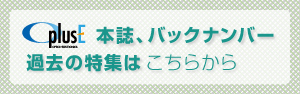

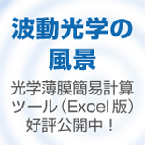







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)