光学部の人たちが取り組んでいる課題を自分ならどうするだろうという立ち位置で考えたり議論することができたのは,結果的に「光学一筋」だったせいだと言えるかもしれません(後編)元(株)ニコン 鶴田 匡夫
 OplusE1・2月号からの2回シリーズの後編。前編では,日本光学に入社して検査部から研究部に配属され,干渉計やホログラフィーの論文発表にいたるまでの経緯や体験などをお伺いしました。後編では,入社して20年経ったころからのお話を伺います。
OplusE1・2月号からの2回シリーズの後編。前編では,日本光学に入社して検査部から研究部に配属され,干渉計やホログラフィーの論文発表にいたるまでの経緯や体験などをお伺いしました。後編では,入社して20年経ったころからのお話を伺います。
光学の専門家であり続けたいという決心
聞き手:次はカメラ事業部への異動ですね。鶴田:入社後20年の夏でした。来るものが来たという感じでした。役員室に呼ばれ,ニコンカメラの生みの親・育ての親で当時副社長だった更田さんから,「カメラ事業部に行ってもらうよ」と言われました。その日が田中角栄元首相が逮捕された1976年7月27日だったのでよく覚えています。更田さんがどんなお考えで私をカメラ事業部に送り込んだのか分かりませんが,何か特別な技術開発を任せようというのではなかったようで,私はカメラ技術部次長生産技術課担当を皮切りに,専用工場の建設を含む普及型一眼レフ生産体制の立案と実施プロジェクトリーダー,品管部・技術部・設計部・電子画像部などの部長を務め,在籍10年の1986年にシステム部の部長に異動するまで,上司も仲間もカメラ作りのプロ達の中で私に何ができるかを自分に問い続ける毎日でした。この期間は主力製品である一眼レフに関してカスタムICを内蔵した露光の自動化に始まりピント合わせの自動化のめどが付くまで,その結果,カメラ人口が飛躍的に増大したときと重なります。ときに辛辣な言葉を吐く大頭仁先生(早大理工,2019年没)が何かの折に,「日本光学って会社は不思議な会社だ。今度こそ電車に乗り遅れると思って回りを見渡すと,誰かがちゃんと乗っている」と言われたことを思い出したりしたことでした。とまれ,私はこの間企業のダイナミックスの真只中にいると実感したことでした。
聞き手:管理職としての仕事がめまぐるしく変わっても,技術者としてのいわば根っこは光学だったのですね。
鶴田:私は1987年に取締役に選任され,その翌年に光学部長,ついで光学本部長に就任しました。やっと古巣に戻ったように感じました。しかし,実際には光学設計部に所属したことも,特定のレンズを設計したこともありませんでした。それでも古巣というのはおかしいのですが,私は日本光学に入社して2~3年たった頃から,応用光学とか光学器械の開発が意味する技術の内容が時代と共に変わっても,その専門家であり続けたいと秘かに考えるようになっていました。
1966年5月に初めての外国出張で参加した国際光学会議(ICO)の会期中に,パリの下町モンパルナスの場末の食堂で,バケツに入ったムール貝のスープ煮をつまみながら,「一人くらい光学一筋でいく奴がいてもいいよな」などと語り合ったのが,辻内順平さん(当時機械試験所,後に東工大),佐柳和男さん(キヤノン,当時USAのZygo社に出向中,1991年没),それに私の3人でした。全員30代でした。佐柳さんは61歳で亡くなりましたが,彼を含めて3人とも,あの時の強いて言えば決意表明に忠実だったことになりましょうか。
具体的に説明するのは難しいのですが,論文を書かなくなってからの長い不在があったにもかかわらず,光学部長・光学本部長時代を通じて大方の部員が取り組んでいるup-todateな課題を同じレベル,すなわち自分ならどうするだろうという立ち位置で考えたり議論することができたのは,結果的に「光学一筋」だったせいだと言えるかもしれません。その中で,当時ニコンに在籍していた渋谷眞人君(東京工芸大学名誉教授)との実に楽しかった議論は「像強度の解析的公式と投影光学系リソグラフィーの実用解像度」の表題で光学*に掲載されました。研究論文の著者に私が名を連ねた,これが最後だったと思います。ともあれ,平取締役時代の大半をここで過ごした5年間は難しい問題を抱えながらあとあとまで影響を残すような決定を強いられる厳しい時期だったにもかかわらず楽しいものでした。
*渋谷,鶴田:21(1992), p.688
「私の光学」を体系化した『応用光学Ⅰ,Ⅱ』
聞き手:『光の鉛筆』シリーズをお書きになったきっかけは本誌2020年5・6月号の受賞記念対談で伺いましたが,『応用光学Ⅰ,Ⅱ』(培風館,1990)をお書きになった経緯をお話し下さい。鶴田:1985年の夏に兵藤申一先生(東大工・物理工学,2015年没)から電話があり,相談したいことがあるので会いたいとのことでした。用件は,先生が培風館から出版予定の『応用物理工学選書』の編集を引き受けたので,その一冊に「応用光学」を加えたい。ついてはその著者をお願いしたいとのことでした。その時私は大学で講義した経験はなく,ドラフトらしいものも手許にありませんでしたが,先生から「応用物理学あるいは物理工学とは,取り扱う対象よりも対象に取り組む姿勢そのものの中に特質があるという観点から,テーマよりどういう著者にお願いするかということを優先した」と言われ,返す言葉もなく有り難くお受けした次第です。私は光学の知識を必要とする職業人がめいめいに個性的で標準的教科書とは大きく偏っているかも知れない「自分自身の光学」をもっていて,それを元手に仕事をしていると常々考えていましたから,先生のお考えがすとんと腑に落ちたのでした。
この時私はカメラ設計部長の職にあって,ミノルタα7000(1985年2月発売)に先を越されたボディー駆動の本格的自動焦点一眼レフ開発の遅れを挽回しようと懸命で,時間的にも気持ちの上でも本の執筆に取り掛かる余裕はありませんでした。しかし,年が明けた86年4月に新製品F501の発売に漕ぎつけ,同じ頃私は定年と同時に東京工芸大学に転出した一色さんの後任としてシステム部長を命じられました。この頃から少しずつ資料の整理やドラフトの作成を始めた次第です。
私がこの本の読者に想定したのは,大学や大学院で講義したことがないことを逆手に取って,1990年頃に光学と光学器械の専門家を目指す人たちでした。彼らが知っていると役に立つと私が考える原理や例題を,私の経験に即してできる限り盛り込みたいと考えました。その結果1冊の中には収まらず2分冊になってしまいました。章立ては光の伝播・幾何光学・回折・干渉・偏光と月並みでしたが,内容に関してはそれぞれの古典的描像とそれから導かれる応用への道筋,具体的な例題の選び方などによって「私の光学」の体系を表現できたと自負しています。好意的な書評をいくつか頂きましたが,その中で黒田和男先生が,「鶴田匡夫の『応用光学』は力作である。―中略―その内容は相当に高度で,大学院の講義でも難しすぎるかも知れない。専門家向けの参考書である。筆者がこの本に感じるのは,内容の信頼度が高いということである。どんなに注意深く書かれた本でも完璧なものはなく,何かしら間違いはあるだろう。その点『応用光学』に書いてあるのなら大丈夫という安心感を与えてくれる。」と書いて下さったのは刊行後13年たった2003年,「光学」*誌上でした。それまで,私は間違ったことを書いていないか,論旨に無理がなかったか気になって仕方がありませんでしたので,ほっとしたことを覚えています。しかし売れ行きの方は芳しくなく,Ⅰ・Ⅱとも5,000部を越えませんでした。この部数を越えれば印税が2%上がって12%になる契約だったのでちょっと残念でした(笑)。
*光学教科書あれこれ, 光学, Vol. 32, p. 377(2003)
<次ページへ続く>

鶴田 匡夫(つるた・ただお)
1933年 群馬県北甘楽郡富岡町(現 富岡市)生れ 1956年 東京大学理学部物理学科卒 同年 日本光学工業 (現 ニコン)に入社 1967年 工学博士 1987年 取締役 1993年 常務取締役開発本部長 1997年 取締役副社長 2001年 退任●専門分野
応用光学
●主な受賞歴
1964年 第5回応用物理学会光学論文賞
2004年 第4回応用物理学会業績賞(教育業績)
2019年 第3回光工学功績賞(高野榮一賞)
●著書
『光の鉛筆』11冊シリーズ
『応用光学Ⅰ』(1990) 『応用光学Ⅱ』(1990)









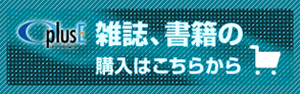
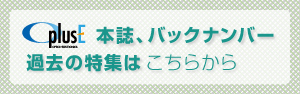

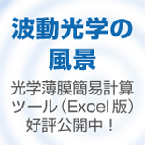







![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)