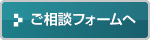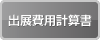セミナーレポート
ニューノーマルにおけるロボットビジョン研究産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター 堂前 幸康
本記事は、画像センシング展2021にて開催された特別招待講演を記事化したものになります。
ロボット研究からのコロナ対策
製造・物流現場では,コロナの影響で,密を避け,移動を減らす「遠隔化」が加速しています。例えば,東京の技術者が南アフリカの高度なロボットを操作し,現地の日本製設備を修理するといったことが挙げられます。ロボットは本来,人の作業を代替し,生産性・効率を改善する手段でした。しかし,現場では,ロボットビジョンやAIを活用した作業能力の向上や,変化に柔軟に対応するための作業学習能力や対話能力の向上,遠隔操作能力の獲得などが重要になってきています。ロボット研究者の観点からのロボットに対するポジティブな意見としては,ロボットの中でウイルスは増えない,人と人の接触を避けることができる,ロボットは作業の効率を高める,といったことが挙げられます。ただし,作業の効率を高めるためには,基本的なロボットの能力を上げなければいけないという課題があります。また,高齢者はリスクが高く,ロボットは介護面でも重要で,高齢の職人の技を遠隔で学びたいといったことや,診断の自動化,検査試薬に対する作業の自動化も期待されています。
物流については,配送の自動化・無人化が大きなポイントになっています。臨機応変に人との接触を避ける物流手段として,宅配モバイルやドローンの研究が加速しています。また,製造については,本来,人の手で行われてきた作業をいかにロボットに代替させるかが重要になってきています。安全性,生産性,そして対人件費の費用対効果が課題です。ただし,対人件費では,密を避けるための付加価値が考慮されるようになってきています。
コロナの影響とは別にしても,製造業においては,人の隣りに置いても安全に作業ができるような協働ロボットが引き続き大きなインパクトをもっています。一方,物流では,器用なマニピュレーションやモバイル,複数ロボット操作,ロバストなコンピュータービジョンの実現が課題になっています。製造・物流では,技術的には,広い意味で人・機械協調技術と,それを支える機械としての安全性・性能の基盤が重要になっています。
<次ページへ続く>

産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター 堂前 幸康
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所主席研究員を経て,国立研究開発法人産業技術総合研究所に入所。現在,インダストリアルCPS研究センター オートメーション研究チーム長。同所人工知能研究センター付き,大阪大学招聘教授,奈良先端科学技術大学客員教授を兼務。パターン認識やロボティクスの産業応用に関する研究開発に従事。米国R&D100賞,情報処理学会喜安記念業績賞など受賞。博士(情報科学,北海道大学)