新しいことをやりたいと思ったら,周囲が良いと言っている現実を否定しなさいハイウィッツ・テクノロジー 米澤 成二
アイデンティティー
会社は研究者に新しいことを提案してほしいといっていますが,実際に新しいことを提案しはじめると周囲から妨害,中傷が起こるのです。要するに,あいつはおかしなことをいっていると。だから自分がこれは必ず将来ものになると確信したら,その技術を外に発信するのです。社外の人と交流し,学会に論文を発表してよその人に見てもらうことをよくやりましたよ。社内評価だけでは潰されるのです。評価しようとしないのですね。 実際に経験したものに,1985年に5.25インチの光磁気ディスクで,データを記録するガイドになるグルーブ溝にウォブルマークを併用すると,今後の高密化に寄与できると,私は2年間かけて実験と計算を繰り返して社内提案を行い,学会発表もしました。しかし,社内では聞く耳をもってもらえず,結局規格化提案は駄目になってしまいました。社内には周囲に有能な研究者も多くいて,皆さん馬鹿ではありませんから,技術的には分かっても,どちらに味方したほうが昇進と業務評価にプラスになるか,天秤にかけるのですね。ところが,10年後の1995年7月にありましたDVD-RAMの規格化会議に,当時の私のその実験データが無断でもち出され,グルーブ溝にウォブルマークを併用する効用を提案しているのです。これはDVD-RAMの規格になり,会社としては戦略的にポイントを稼いだ訳ですからいいのでしょうが,研究の良心はどこにあるのだろうと,あきれかえってしまいます。
実際に経験したものに,1985年に5.25インチの光磁気ディスクで,データを記録するガイドになるグルーブ溝にウォブルマークを併用すると,今後の高密化に寄与できると,私は2年間かけて実験と計算を繰り返して社内提案を行い,学会発表もしました。しかし,社内では聞く耳をもってもらえず,結局規格化提案は駄目になってしまいました。社内には周囲に有能な研究者も多くいて,皆さん馬鹿ではありませんから,技術的には分かっても,どちらに味方したほうが昇進と業務評価にプラスになるか,天秤にかけるのですね。ところが,10年後の1995年7月にありましたDVD-RAMの規格化会議に,当時の私のその実験データが無断でもち出され,グルーブ溝にウォブルマークを併用する効用を提案しているのです。これはDVD-RAMの規格になり,会社としては戦略的にポイントを稼いだ訳ですからいいのでしょうが,研究の良心はどこにあるのだろうと,あきれかえってしまいます。課長がいて,部長がいて,所長がいる。すると,上長の機嫌をいかにとるか,その任期の間にいい点を取らなくてはいけないということになります。昇進に響きますから5年も10年もかかる新しい技術,つまり世の中で煙も出ていないような話題は,全然意味がないのです。社内の誰にとってもメリットはないのです。
私は大阪大学で学位を取ってすぐの,1967年の春にアメリカに渡りました。大学での学位論文「領域型レンズ自動設計法」という新しい論文がロチェスター大学の光学研究所に着目され,その研究を向こうで続けるためでした。
向こうで感じたのは,ミミズの博士でもノミの博士でもいい,どんなつまらないものでもいいから,生きていくためにはその分野で世界一になればいいということでした。アメリカはそういう意味でいろんなチャンスがある,広い国だと思いましたね。そのためには自分のアイデンティティーというのをもっていなければいけない。他人がこうやっているからこうやりますということは,もう二番煎じなのです。研究室での朝は,コーヒータイムでの「What is new today?」で始まり,お前のアイデアは何なのか,お前は何をしたいのか,何を主張するのかから話が始まるのです。そういう考えを私が抵抗なく受け入れられたのは,卒業したのが阪大であって,官僚養成大学的な東大とは違ったバンカラさの影響だと思います。20代にアメリカで経験した,議論とはこのようなものであるというこの思いが,先ほどの光ディスクのように,議論の不透明性によって打ち壊されたわけです。非常にショックでした。それがあってから,私の研究の主張と成果というものを風化させないように,『光記録―研究と特許―』として自費出版しているのです。これは今も続いています。







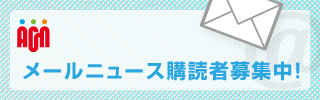
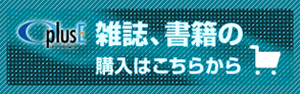
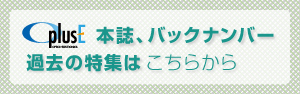
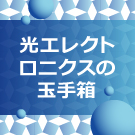
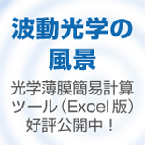



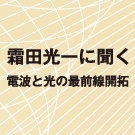
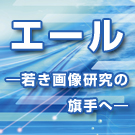


![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)