第18回 台湾交流録 part 4 次から次へ
ホログラフィー講座続く
HODIC in Taiwan 3の翌年,すでに交通大学に移っていたDr. Hsiehから連絡がきた。交通大学光電研究所所長のProf. Ken Hsuの提案で,ホログラフィーの夏季集中講座を開講したい。ついては講師として招聘したいという内容であった。考えてもみなかった申し出に,驚きと同時に「やったー!」という気分であった。師範大学では,2009年の“ホログラフィー入門”を最後に,結局講座は継続されず,がっかりしていた時だったからだ。もちろん,二つ返事でYESである。Ken Hsu教授は,辻内研の留学生であるSu教授の同僚で,台北での展覧会や常設作品のオープニングなどには,一緒に新竹からよく駆けつけてくれた人物である。実はこの前年,Su教授は病に倒れ,悲しいことに急逝されてしまった。彼は病を知ったとき,後に残される研究室の学生たちを案じて,残りの指導をKen Hsu教授に託したのだと伺った。
集中講座はその夏に開催することになった。2013年6月であった。講座初日のシンポジウムではSu教授のメモリアルセクションが設けられ,研究室のOBによる懐かしいスライドが写しだされた。辻内先生も招待され孫弟子たちと対面されたのだった。
交通大学のメインキャンパスは新竹にある。(新竹については本誌第16回7・8 月号にもふれたとおり)立地条件は,台北市中心にある師範大とは天と地ほどの違いだ。ここでは,学生たちに必要なもの,学業のみならず生活のすべてがキャンパス内で賄われている。研究棟のほかゲストハウスや学生寮も完備し,コンビニはもちろん,木陰のカフェテリアや複数点在するレストラン(学食とは言い難いものなど)の充実ぶりには驚かされた。なかでも一番驚いたのは,多くの素晴らしい現代彫刻が敷地内に点在して設置されていたことだ(図6(a)(b))。そして,これらの作品のすべてが楊英風(本誌第15回5・6 月号掲載)作だったことである。まさかここでこんなに多くの楊氏の作品に再会するとは! 懐かしさと同時に何故ここに?という疑問が湧いた。芸術系の大学ならいざ知らず,理工系大学でこのような芸術作品があたりまえのように庭に設置されている様子は,例えば,MIT(マサチューセッツ工科大学)ではカルダーの大きな野外作品が裏庭の芝生の中にさりげなく設置されていたりするが,日本国内ではほとんど見ることのできない光景である。緋鯉が泳ぐ池のある庭園や美しく花を咲かせる蓮池(図6(c))の側には,椅子や遊歩道も整備されていた。実は,私が交通大学を訪問するのはこの時が最初ではない。2005年の新竹ITRIでのHODICの後,Su教授が大学を案内してくれた。しかし,その時は優雅な遊歩道も野外彫刻もまったく見当たらなかった。聞くところによると,前任の学長が,よい学びと研究は素晴らしい環境から生まれるという信条を基に学内の大改革を行い,キャンバス内を整備していったのだそうだ。楊英風は台湾の現代彫刻の第一人者であるが,学長は楊氏と懇意の間柄で,楊氏は多くの作品を寄贈されたのだそうだ。
 閑話休題。ホログラフィー講座はDr. Hsiehとの共同担当で,準備も進行も“あ,うん”の呼吸で順調に行われた。講座参加者には,ディスプレイホログラムに興味を持つ学内の研究者らも顔を出した。その中の1人から声を掛けられた。Bulgarian Academy of Scienceの教授で,現在は交通大学に客員教授で教鞭をとっている人だった。彼女は,指導を受けた教授から私のことをよく聞いていたと言うのだ。はて? ブルガリアと聞いて,そういえばノースウエールズのISDH(2006)で,「久しぶり」と声を掛けられ,レイクフォーレストのシンポジウム以来20数年ぶりに,懐かしく再会した人物を思い出した。1980年代初頭はまだ東西冷戦が続き,東欧からアメリカへの渡航が難しい時代,ブルガリアから若い研究者がISDHに出席したのだ。ブルガリアからの参加者というので目立つ存在だったが,1週間キャンパス内でともに過ごすうち,羽目を外しそうなほどひときわ解放感を楽しんでいる彼の言動がとても印象的だったことをよく覚えていた。再会した時は,ブルガリアのアカデミーで光学界の重鎮になっていた。縁とはこのことか。世界は小さい! 図7(a)は,受講生たちが制作した被写体である。ワンステップレインボウを制作し,記録材料はケミカルの現像処理を必要としないフォトポリマーを使用した。図7(b)は,最終日の展示風景である。学外からも数名の参加希望の受講生を受け入れていたことは興味深かった。その中には新竹出身でロイヤルカレッジオブアートに留学中の,ホロを学び,ちょうど帰国中で受講したという女子学生もいた。
閑話休題。ホログラフィー講座はDr. Hsiehとの共同担当で,準備も進行も“あ,うん”の呼吸で順調に行われた。講座参加者には,ディスプレイホログラムに興味を持つ学内の研究者らも顔を出した。その中の1人から声を掛けられた。Bulgarian Academy of Scienceの教授で,現在は交通大学に客員教授で教鞭をとっている人だった。彼女は,指導を受けた教授から私のことをよく聞いていたと言うのだ。はて? ブルガリアと聞いて,そういえばノースウエールズのISDH(2006)で,「久しぶり」と声を掛けられ,レイクフォーレストのシンポジウム以来20数年ぶりに,懐かしく再会した人物を思い出した。1980年代初頭はまだ東西冷戦が続き,東欧からアメリカへの渡航が難しい時代,ブルガリアから若い研究者がISDHに出席したのだ。ブルガリアからの参加者というので目立つ存在だったが,1週間キャンパス内でともに過ごすうち,羽目を外しそうなほどひときわ解放感を楽しんでいる彼の言動がとても印象的だったことをよく覚えていた。再会した時は,ブルガリアのアカデミーで光学界の重鎮になっていた。縁とはこのことか。世界は小さい! 図7(a)は,受講生たちが制作した被写体である。ワンステップレインボウを制作し,記録材料はケミカルの現像処理を必要としないフォトポリマーを使用した。図7(b)は,最終日の展示風景である。学外からも数名の参加希望の受講生を受け入れていたことは興味深かった。その中には新竹出身でロイヤルカレッジオブアートに留学中の,ホロを学び,ちょうど帰国中で受講したという女子学生もいた。
 <次ページへ続く>
<次ページへ続く>








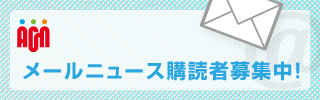
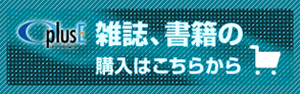
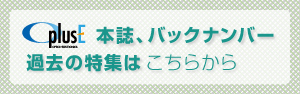
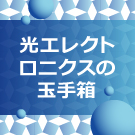
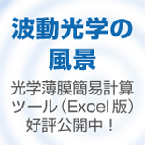



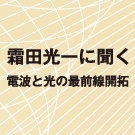
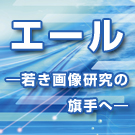


![研究室探訪vol.30 [奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室]](https://www.adcom-media.co.jp/wp-content/themes/adcom/scripts/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2022/11/laboratory1.jpg&w=80&h=100&zc=1&q=100)